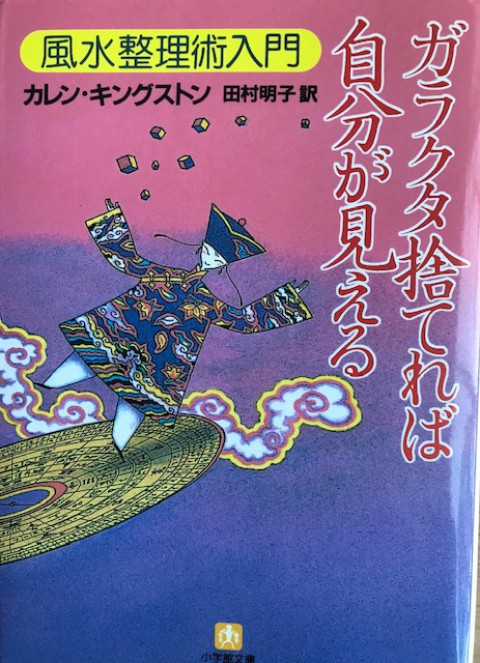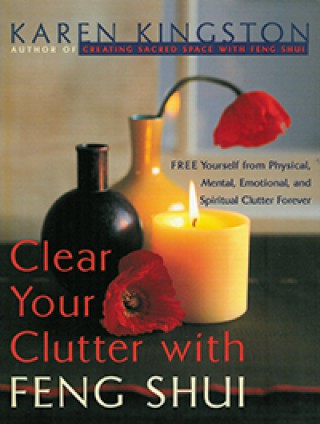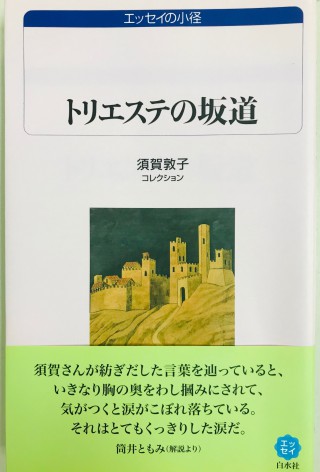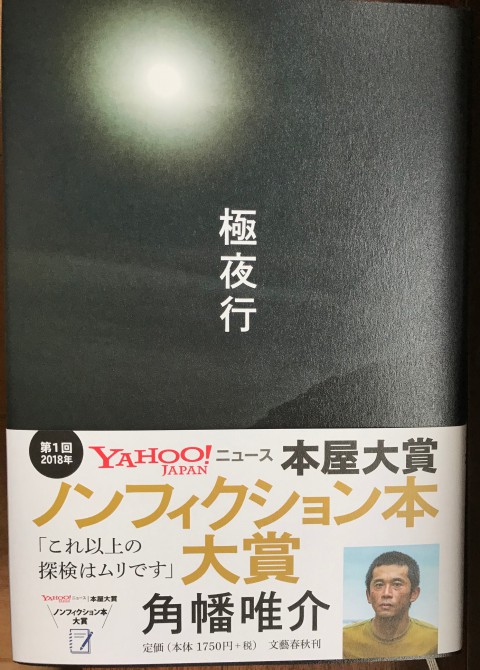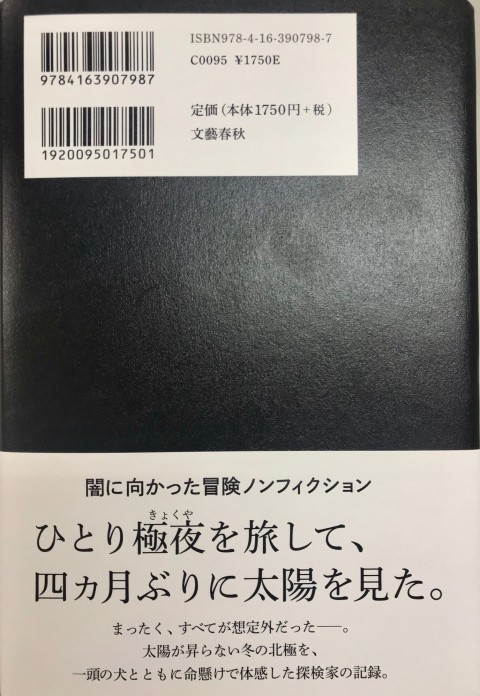有元美津世著『ロジカルイングリッシュ』
2020年04月05日
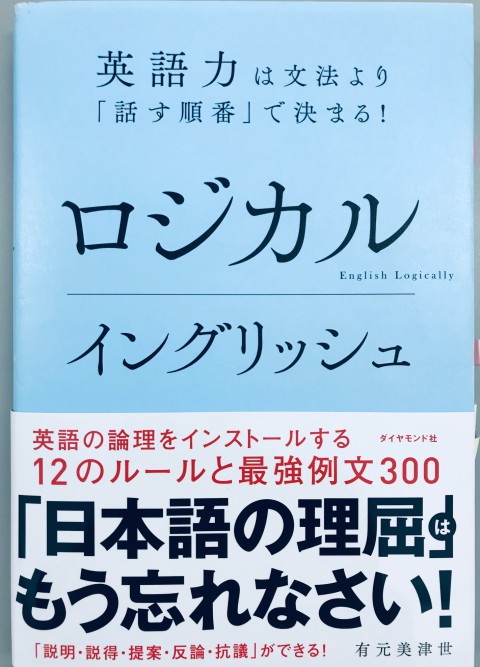
有元さんの本には、これまでもとてもお世話になってきました。特に『英文ビジネスeメール実例集』は、今ほどウェブ翻訳サービスが充実していなかった時代、本当に重宝しました。
有元さんは、大学卒業後、日米の企業勤務を経て渡米。日本企業のアメリカでの立ち上げに携わり、MBA取得後、独立。16年間、日米企業間の戦略提携コンサルタントとして活躍。現在は投資家として世界経済の動向を追い続けています。最近はコロナウイルス関連の海外メディア報道を和訳してSNSでこまめに発信中。在米35年。
さて今回紹介するのは『ロジカルイングリッシュ』(2015年出版)という本です。この本が提案しているのは、英語を論理的に伝える技術を身に付けようということです。
(以下は本文より)
日本人の書く英語でよく見かけるのが、文法的には正しいのに英語圏の人には伝わらない英文です。その主な要因は―
1. 日本語の単語を英語に置き換えているだけの直訳である
2. 非常に簡単なことを、やたら複雑な文で言おうとしている
3. and や butなどの接続詞で文はつながっているのだが、論理が飛躍していて、文と文のつながりが分からない
他にも日本人によくある誤解に、Pleaseを付ければ丁寧表現だと思うかもしれませんが、Pleaseは命令の場合が多く、上司に対しては使えません。メールでもPlease reply promptly. と書くと「すぐに返事ください」という命令になってしまいます。
また、expect と hope も同じ意味のように考えているかもしれませんが、expect は「当然起こるものと思う」ことで、使い方によっては「当然のこととして要求する」という意味になります。だから、I expect to hear from you. などと書いてしまうと「ちゃんと返事をください」という相手への要求になり、Please respond. よりもさらに高圧的なのです。
そして、日本語のビジネスメールでは頻繁に使われる「それはちょっと難しいです」という表現をそのまま It’s a little difficult. と書くとトラブルになりかねません。この表現では、交渉の余地があるという期待を持たせてしまうからです。ですからdifficult は使わず、We are unable to discount the price. (値引きはできません) というようにはっきりと伝えることがとても重要です。―
つまるところ、誤解を生まない表現がビジネスメールではまず基本だと言えますね。メールに限らず、翻訳で最も気を付けたいことです。(H.S)